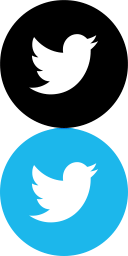映画『i ai』ロングインタビュー
マヒトゥ・ザ・ピーポー×佐内正史
幻想、現実を点滅して往き来きする
バンド「GEZAN」のフロントマンであり、文筆家としても活動するマヒトゥ・ザ・ピーポー。彼が初監督をつとめる映画『i ai』の劇場公開がはじまった。
『i ai』は監督マヒトの実体験をもとにした作品。舞台となったのは、瀬戸内海をのぞむ兵庫・明石の街。破天荒なミュージシャン・ヒー兄(森山未來)に吸い寄せられていく、バンドマンのコウ(富田健太郎)、恋人のるり姉(さとうほなみ)、ヤクザの久我(永山瑛太)たちの姿が映し出される。
映画の話を聞こうと、『i ai』を撮った監督マヒトさんと撮影監督の佐内正史さんを喫茶店に誘った。自由なふたりの会話は、映画の舞台となった兵庫から、はたまたインドの神々やアイヌの口伝、死後の世界にまであちこちにトリップしていってーーー。

―――マヒトさんは音楽、佐内さんは写真をやっていて、映画をつくるのは今回が初めてのことでしたね。映画をとおして、ふたりが見ていた風景について話を聞かせてください。まず、映画『i ai』を観終わったあと「これはなんだったんだろう」という、掴みきれない衝撃がありました。ストーリーも、シーンも、登場人物も、街も、それぞれがまとまらずに、断片的に網膜に焼きつくような作品でした。
佐内:まとまっていないように感じるのは、あんまり社会性がないってことなのかな。ものすごくまっすぐに撮っていたよね。
マヒト:社会性は......弱いかもしれない(笑)。奇をてらったわけではないんだけどね。
ずれているとされる感覚をもつ人はたくさんいると思うんだけど、そのことがあんまり許されないような、無言の先入観みたいなものが社会につくられてる気がして。ほんとは世界ってものすごく複雑で歪な形状をしてるじゃないですか。

マヒト:この間、「明日、インド行こ」って思い立ってコルカタに行ってたんだけど、イスラームもヒンドゥーも仏教もいろんな宗教があって、ベロ出して生首ぶら下げてる神様がいたり、ヒンドゥー教で神様とされている牛が通り一本渡ったたら肉になって吊るされて売られてたりして。道を歩いていても、あおり運転っていう言葉もないくらい車が走っていて。車道の線はあるんだけど、このスペースのなかだったらどう動いてもある程度許されるみたいな。
そのくらい人間って複雑な世界を平然と生きてる。いい人、悪い人、優しい人、こわい人......いろんな形容があるけど、そんな言葉で回収できないくらい複雑で入り乱れているものですよね。
それこそ違う国に行ってみたら、自分たちが絶対的な常識だと思っていたものが、ただの選択された一個の常識でしかないことがわかる。旅もそうだけど、映画でも写真でも音楽でも、そういう提案が表現の役割だと思う。
佐内:そうね。いまマヒトの話を聞いてて思ったのは、昔から日本にいても海外にいても、どこにいても、自分はどうやらずっと旅してるような感覚があるんだなって思い出した。メキシコにいても日本にいても、「えぇ、なんだろうこの国」っていつも驚いてる。
マヒト:ずれてるなっていう現在地も感じつつ、はずれてても生きてていいじゃんって気持ちがあるから、既存のルールや求められた枠に合わせて映画をつくろうとははなから考えなかったですね。言葉だって、江戸時代に生きてた人と現代のギャルが使う言葉は違うけど、どっちが正しい間違っているとかではないし。そこは怖がらずに映画をつくれたのはよかった。

マヒト:最近、デヴィッド・リンチの『ストレイト・ストーリー』を観ていて、自分のなかにぎゅっと入ってきたんですよね。それまでロードムービーは退屈でぐっとこなかったんだけど。映画の公開準備があって疲れてたのかもしれない(笑)。ここから抜け出したい、遠くに行きたいっていう気持ちは、旅とワンセットなんだと思う。
佐内:俺、リンチは好きでほとんど観てるけど、『ストレイト・ストーリー』は観てないな。観たくなっちゃった。
マヒト:いいんですよ。トラクターに乗っておじいちゃんがゆっくりゆっくり旅するんです。リンチこんなのもつくれるんだって。またインドの話をしていいですか。映画の話をしながら、やっぱり頭の片隅にコルカタの風景が浮かび上がってきちゃってるんですよね(笑)。
道を歩けば貧富の差が目に入ってきて、神様もいっぱいいて、そういうものを目の当たりにしながら、食堂に入ってお皿の上でいろんな種類のカレーを手で混ぜて、手についた菌とカレーをごちゃ混ぜにして食べて......。そうやってカレーを食べながら、自分はなんだかインドの神様のことがわかった気がしたんですよね。

マヒト:一神教みたいに一つの圧倒的な光を確定しておいたほうが、みんなを導きやすいというのはわかる。ただ、一つの神様がいてそこに全て依存する形でついていこうとするのって、だんだん余裕がなくなってくるんじゃないかなって思う。
多神教のようにたくさんの神様がいる世界って、真ん中からはずれた神様も許容していて、本来としか言えないけど日本も水の神様もいればトイレの神様もいる八百万の国じゃないですか。百個の神がいて百個の答えを提示してというのは健全だと思う。
映画の話に戻ると、はみ出てる人がいっぱいでてきたり、何回観ても話を回収しきれないっていうのは、そういう複雑さの肯定にもつながってくる。
映画の一つひとつのシーンも、登場人物も、それぞれが主役。主人公という意味では、富田健太郎演じるコウがいて、森山未來さんのヒー兄がいるんだけど。麻婆豆腐を食べるシーンには麻婆豆腐の時間がある。鉄板焼の上でジュワーって。


佐内:あの麻婆豆腐、うまかったね。溢れ出してるよね。あのシーンには赤のバトンがあったから、赤でシーンをつないでる。富田(コウ)の時間、瑛太(久我)の時間、イチさんの時間。映画の中にそれぞれの時間が流れてる。
友だちと映画を観にいった帰り道に、喫茶店入って映画の話をしたりするじゃない。自分は映画のシーンの話はするんだけど、みんながあらすじの話をしてるときには「うん、うん」って頷いてるだけだったりする。映画の全体像はみえなくてもいいかなって。
マヒト:俺も佐内さんも、蛇口を開きっぱなしにしてそれを閉めるのを忘れて水中を楽しんでいるようなところがあって、説明をぶっ飛ばしているから、当然説明をもらえるのが当たり前っていう癖がついてる人はわかりにくいかもしれない。
以前、佐内さんから「ふわふわ食べいく?」って誘われて、一緒にパンケーキ食べにいったことがあるんです。それで車に乗ってお店に向かってるときに、「信号が赤になるときに、信号が『恋がしたい』って言うんだよね」って佐内さんが話してたのを覚えてます。だいたい言葉の使い方って、何かの目的を果たすために発するわけじゃないですか。そこがもう佐内さんの場合はエラーしているっていうか(笑)。
ストーリーに起承転結をつけていく方法もあると思うけど、たとえば自分がこうやって会話してるときにも、頭のどこかでまだインドのことを考えててワープしてしまう。アートとして見せたいとかではなくて、それくらい時系列もスキップしていくのって実は健全な状態だと思う。
佐内:そういう表現って必要だと思う。一つのことに留まってしまうと、奥行きが出てくる。奥に考えると争いがある世界に向かっちゃう。飛ぶことで争わない世界の可能性がそこにある気がして。部屋にずっといるわけじゃなくて、外に出て、知らないことを知って、明るくなる。話が飛んでいくっていうのは明るいし平和の可能性があるなって思う。

―――マヒトさんの頭の中を映像化していくのに、ふたりはどうやって意思疎通していたのですか。脚本もマヒトさんが書かれていましたよね。
マヒト:脚本はあるけど、俺が現場に入って最初にする仕事は、役者よりなによりまず佐内さんに口頭でどう撮ってほしいかを伝えてましたね(笑)。口伝って大事だなと今回思った。
それこそアイヌのウポポ(歌)って、楽譜に落としちゃいけないんですよね。「フチ」ってアイヌ語で「おばあちゃん」のことを指すんですけど、それって神様を指す言葉でもあって「〜フチ」っていったりする。年齢を重ねるごとに神に近づいていく文化なんですよね。今、そんなフチ世代しか歌えない歌があって、次の世代に伝えるのに音符と歌詞を楽譜にしたらいいという話もあるんですけど、それでは伝承したことにならないといってアイヌの人たちは全部口伝で伝えようとしてるんです。そんなふうに口伝だけで映画撮る方法ってあるのかな。あったらおもしろいかもね。
映画って遅いメディアじゃないですか。観る側は、わざわざ映画館行って、席に2時間ホールドされて、はじめて向き合える。つくる側にしても、映画撮ってから劇場に流れるまでに『i ai』の場合は3年かかってるし。思ったことをすぐに言葉にできたり写真で表せるメディアに比べて、すごい時間がかかる。
その遅さって重要だと思っていて、どこか旅に近い。自分の身体をその場所まで運ぶって、効率的ではなくて、すごい遅い土地とのコミュニケーションじゃないですか。今、インターネットがあって、ケータイがあって、情報の速度もどんどん加速しているけど、たかだか人間が一日に感知できる情報や獲得できる量って限られてる。それをどこまで感じられるかが豊かさだと思うけど。映画や旅の遅さでしかアクセスできないことってあるんじゃないかな。

マヒト:『i ai』では、コウがEコード引いたら、るり姉の部屋に飛んで最初にヒー兄からEコードを教わったシーンにつながる。時系列を越えて、音で飛んだり、色でつながったり、映画の強みを最大限まで使った気がする。
佐内:買い物とかもそうだよね。ネットでものを買うって、便利で時間が増えるような気がするけど、逆に時間がなくなってるんだなって思う。スーパーで買い物をすると、緑道を歩いて、甲州街道を通って、街路樹が風で揺れてるなとか、すれ違った人のことを感じているし、体力も使う。でもネットで買い物をするってことは、そうした時間がなくなることでもある。
写真は時間を止める仕事だから、時間ってなんだろうってよく考えるんだけど、時間って経験しないとなくなってしまうものなんだなって思う。
たとえばパソコンを開いてオンラインで打ち合わせをするのと、こうやって喫茶店で話をするのとも違うじゃない。ここにはコーヒーがあって、このカップとか灰皿とか水の配置も二度とないものだから。
マヒト:オンラインだと振動は共有できないですよね。自分は音の人だから、その違いを感じる。音って全部空気の振動じゃないですか。リモートだと情報と情報はもちろん交換できるんだけど、振動は絶対シェアできてない。やっぱりそれってコミュニケーションの純度が違ってくる。

―――『i ai』のHPに載っているマヒトさんの映画の制作日記のなかで、新神戸駅に降り立って街をロケハンしていて、「カットの構想が街に引っ張られてきられていく」ということを言っていましたね。マヒトさんにとって、明石や神戸はどういった場所なのでしょうか。
マヒト:コウやヒー兄が暮らしていた街は明石で撮っていたんだけど、撮影現場はなんにもない街。周りにコンビニもないし、工業地帯でもないし、道端でヤンキーが花火してるような。気の利いた店ができたら、江の島とか尾道みたいになりそうなんだけど、まだ発見される前の街という感じですね。
佐内:あがらない街。平熱の街。自分は、メインの街ではなくて途中の街がすごく好きで。映画を撮っていたあの場所は、どこまでいっても途中だった。そここそ日本を感じる。荻窪駅と西荻窪駅の間みたいなそういう場所って撮りやすいんですよね。カメラを持たないでいったら、ぼーっと時間が過ぎてしまうような。



マヒト:この映画は旅のような気持ちでつくった部分はありますね。生まれたのは島根で、そのあと引っ越しをしていろんな場所に住んでいたから、これという地元がないんですよね。ずっと根なし草のような感覚があって、帰る場所がなくて行く場所だけがあるような。
ただ最近は行った場所が一個一個、故郷になっていってるのも感じます。『i ai』を撮影した明石も、映画にでてくる景色はやっぱりもう自分のなかで故郷化してるんですよね。
佐内:故郷って、遠くにいて思い出す場所のことなのかな。東京から離れて、NYに住んだら東京が故郷になるし。だからいろいろ故郷があるのは、自然なことだと思う。
マヒト:街とか景色が語りかけてくるのはありますね、絶対ね。やっぱり頭で考えてできるものもあるけど、それが完璧にはまるはずもないから。そこはやっぱり街の演出みたいなものが絶対かかわってくる。それは映画にかかわらずだと思うんですけど。
人があらゆることをコントロールできるとどこかで過信してるところがあるかもしれないけど、街なんて自分の思い通りにならないことで溢れてるじゃない。だから佐内さんが言っていたみたいに、部屋に閉じこもっていないで、窓が開いていて、街に出ていくのが大事なんじゃないかな。
―――『i ai』には、ストーリーの本筋にかかわってくるかどうかわからない街の人たちが映画のなかに散りばめられていますよね。それがあの街だと、あの映画だと、とても自然なことのように映りました。
マヒト:ハナレグミの(永積)タカシさんが東京国際映画祭で『i ai』を観てくださったときに、「誰一人芝居してなかったね」って言ってくれて、その言葉はけっこううれしかったな。みんななんか自然とそこにいたっていう。もちろん基本的には脚本があって、台詞もあって、役者の経験値もさまざまなんだけど、なにか自然な形でそこに立っているドキュメンタリーともいえるようなものになってる。それだけみんなのなかにちゃんと神戸の海が流れていて、潮風を浴びていたんだと思う。

マヒト:台詞を言わなきゃいけないんじゃなくて、言っているだけ。やらなきゃいけないんじゃなくて、やるだけっていうか。自分はどうしても監督としてその場にいるから、言葉の権限みたいのもいっぱいもってると思うけど、こうしてね、ああしてねっていうふうにコントロールしきりたくなくて。あたかもその人が選んだかのようにいてほしい。自分も揺さぶられようと思っていたし、役者一人ひとりも揺さぶられてほしいと思っていた。
佐内:みんな撮りやすかった。嘘つかずにストレートにカメラの中に入ってきて。それがちょっと寒かったりすると撮りにくくなってくるのかな? そういうのはなかった。
マヒト:ほとんど最初のカットを使ってましたしね。3回以上撮り直したシーンはなかったんじゃないかな。なんだったらもう「テスト本番!」っていって、それでいけるならそれでいっていたしね。
佐内:やっぱりライブだからさ。
マヒト:佐内さんが言っていた「寒くなる」という話でいうと、『i ai』にかかわった人たちがいたから、冷めずにできたんだなとも思う。たくさんの人がかかわる仕事って、波動を共有できなくなることもあるから、そういう意味では映画だって危ない面はあるはずなんだけど、自分の力というよりはそれは十三月(GEZANが主宰する音楽レーベル)のメンバーがいたから、健全なかたちで『i ai』がつくれた。
佐内:GEZANのメンバーが、撮影中の車止めしてくれたり、機材運ぶの手伝ってくれたりしていたもんね。
マヒト:「このシーンはカナブン越しで撮りたい!」っていって、虫取り網を買って朝から捕まえにいってくれたりね(笑)。

―――映画では、絵本のシーンがでてきたり、赤い服の集団がでてきたり、ホームレスのおじさんが言葉を投げかけてきたり、現実と幻想が入り交じるような場面がでてきますよね。そしてヒー兄自体も、現実とそうではない世界をぎりぎりのところで歩くような、ファンタジーのような存在のように感じました。
マヒト:この間、ライブでフィッシュマンズのゲストボーカルをしたんです。その時期は自分があまり調子がよくないときでもあったんですよね。一緒に音楽をやっていた仲間のオライビが死んでしまったのもあったから。
そんなときに、改めてフィッシュマンズの曲に深く潜ってみたんです。(ボーカル)佐藤さんが亡くなる前の最後のほうの曲を歌っていると、佐藤さんが考えていたことが流れ込んでくるような感覚があって。
佐藤さんがあちら側とこちら側の境界線をぱかぱかと点滅して跨いでいくようなところを、詩をなぞりながら感じていました。もう世界のことはどうでもよくなって、自分と彼女とふたりぼっちみたいな、ぐっと極端までクローズにするんだけど、ときどきみんなのことが気にかかって「調子はどうだい?」って外に問いかけたりして。フィッシュマンズの曲は、意識が最初にはじまったときから、どんどん線をまたぐことを怖がらなくなっていく歴史だと直感したんです。

大体の人は死にたくないから、生きる理由を増やすことをしてる。週末遊びにいったり、おいしいごはん食べたり、自分の魂で仕事にかかわるとか......それってこの世界に踏みとどまる理由を探してるんだと思うんですよね。少なくとも俺はそうで、音楽も映画も、仕事の前にそんな活動としてやってるんですけど。
それがだんだん佐藤さんと一緒になって拡張していくと、この世界にとどまりたいというより、向こう側にいくことが怖くなくなっていく。この線より向こう側は想像していること、こちら側は現実に起きていることっていう境目がなくなって、自分の身体がのみ込まれていく。自分にもそういう点滅の感覚があるから、フィッシュマンズを歌いながら引っ張られるような感じがあったりして。

マヒト:たとえば年をとって死に向かっていくときって、思い出だったり頭のなかで想像したことって曖昧になっていくと思うし、本当にあったかどうかってあんまり関係なくなっていくんじゃないかって。肉体がなくなったあとのファンタジーの世界に入っていって、土に還っていく準備をしている。逆にいうと赤ちゃんは無重力のところからやってくるもので。
だからヒー兄がファンタジーというのはそのとおりだと思うし、それと同時にそういうふうに向こう側とこちら側を行き来すること自体も健全なことなんじゃないかって思う。
もちろん佐藤さんが亡くなったことを寂しいと思う人もいっぱいいるだろうし、ヒー兄だってそう。でも俺からすると、現実とされてる世界のほうが、真実と真実の間の仮の時間のような気持ちがある。だって生まれてくる前と死んでいく後の間に挟まれた時間なわけですよね。現実のほうがなんか嘘っぽいんじゃないかって。佐内さんの写真とか詩とかも、そういう世界の感覚を前借りしてるんだと思うよ。

―――映画ではヒ―兄がいなくなった後の、コウやるり姉たちのそれぞれの時間も丁寧に描かれていますよね。そして一気にラストに向かっていく。
マヒト:ヒ―兄のいない世界を撮ることで、ある程度の翻訳としてのやさしさを残しています。
キラ(ヒー兄の弟)と子どもが絵本を読んでいるシーンで、ぱっと窓の外をみたときに造花の花が咲いていたり、その赤い花が風で運ばれてライブハウスに落ちていたり......。そうやって身体が亡くなっても、別のものに置き換わったり、誰かの意志として残ったりして、生かすことができる。
マヒト:それってつくるものにもいえることで、佐内さんの写真集だってその写真の被写体も写真のなかで永遠に生きてるじゃないですか。
いろんなかたちで自分のドッペルゲンガーみたいなもうひとつの私を細かく刻んで、置いていってるんだと思う。こうやって会話していても、相手のなかに自分の存在を置いてきたり、その人の記憶に自分の住所をつくって、故郷をつくってしまうことを、みんな自然とやっているんですよね。

監督・脚本・音楽:マヒトゥ・ザ・ピーポー
富田健太郎、森山未來、さとうほなみ、堀家一希、永山瑛太、小泉今日子、吹越満、大宮イチ
撮影:佐内正史
劇中画:新井英樹
製作プロダクション:スタジオブルー
配給:パルコ
https://i-ai.jp/

『i ai』は監督マヒトの実体験をもとにした作品。舞台となったのは、瀬戸内海をのぞむ兵庫・明石の街。破天荒なミュージシャン・ヒー兄(森山未來)に吸い寄せられていく、バンドマンのコウ(富田健太郎)、恋人のるり姉(さとうほなみ)、ヤクザの久我(永山瑛太)たちの姿が映し出される。
映画の話を聞こうと、『i ai』を撮った監督マヒトさんと撮影監督の佐内正史さんを喫茶店に誘った。自由なふたりの会話は、映画の舞台となった兵庫から、はたまたインドの神々やアイヌの口伝、死後の世界にまであちこちにトリップしていってーーー。
text = MAKI TSUGA(TRANSIT)

映画や音楽の表現と、旅の共通項。
―――マヒトさんは音楽、佐内さんは写真をやっていて、映画をつくるのは今回が初めてのことでしたね。映画をとおして、ふたりが見ていた風景について話を聞かせてください。まず、映画『i ai』を観終わったあと「これはなんだったんだろう」という、掴みきれない衝撃がありました。ストーリーも、シーンも、登場人物も、街も、それぞれがまとまらずに、断片的に網膜に焼きつくような作品でした。
佐内:まとまっていないように感じるのは、あんまり社会性がないってことなのかな。ものすごくまっすぐに撮っていたよね。
マヒト:社会性は......弱いかもしれない(笑)。奇をてらったわけではないんだけどね。
ずれているとされる感覚をもつ人はたくさんいると思うんだけど、そのことがあんまり許されないような、無言の先入観みたいなものが社会につくられてる気がして。ほんとは世界ってものすごく複雑で歪な形状をしてるじゃないですか。

©STUDIO BLUE
マヒト:この間、「明日、インド行こ」って思い立ってコルカタに行ってたんだけど、イスラームもヒンドゥーも仏教もいろんな宗教があって、ベロ出して生首ぶら下げてる神様がいたり、ヒンドゥー教で神様とされている牛が通り一本渡ったたら肉になって吊るされて売られてたりして。道を歩いていても、あおり運転っていう言葉もないくらい車が走っていて。車道の線はあるんだけど、このスペースのなかだったらどう動いてもある程度許されるみたいな。
そのくらい人間って複雑な世界を平然と生きてる。いい人、悪い人、優しい人、こわい人......いろんな形容があるけど、そんな言葉で回収できないくらい複雑で入り乱れているものですよね。
それこそ違う国に行ってみたら、自分たちが絶対的な常識だと思っていたものが、ただの選択された一個の常識でしかないことがわかる。旅もそうだけど、映画でも写真でも音楽でも、そういう提案が表現の役割だと思う。
佐内:そうね。いまマヒトの話を聞いてて思ったのは、昔から日本にいても海外にいても、どこにいても、自分はどうやらずっと旅してるような感覚があるんだなって思い出した。メキシコにいても日本にいても、「えぇ、なんだろうこの国」っていつも驚いてる。
マヒト:ずれてるなっていう現在地も感じつつ、はずれてても生きてていいじゃんって気持ちがあるから、既存のルールや求められた枠に合わせて映画をつくろうとははなから考えなかったですね。言葉だって、江戸時代に生きてた人と現代のギャルが使う言葉は違うけど、どっちが正しい間違っているとかではないし。そこは怖がらずに映画をつくれたのはよかった。

コウの時間も、麻婆豆腐の時間も。
マヒト:最近、デヴィッド・リンチの『ストレイト・ストーリー』を観ていて、自分のなかにぎゅっと入ってきたんですよね。それまでロードムービーは退屈でぐっとこなかったんだけど。映画の公開準備があって疲れてたのかもしれない(笑)。ここから抜け出したい、遠くに行きたいっていう気持ちは、旅とワンセットなんだと思う。
佐内:俺、リンチは好きでほとんど観てるけど、『ストレイト・ストーリー』は観てないな。観たくなっちゃった。
マヒト:いいんですよ。トラクターに乗っておじいちゃんがゆっくりゆっくり旅するんです。リンチこんなのもつくれるんだって。またインドの話をしていいですか。映画の話をしながら、やっぱり頭の片隅にコルカタの風景が浮かび上がってきちゃってるんですよね(笑)。
道を歩けば貧富の差が目に入ってきて、神様もいっぱいいて、そういうものを目の当たりにしながら、食堂に入ってお皿の上でいろんな種類のカレーを手で混ぜて、手についた菌とカレーをごちゃ混ぜにして食べて......。そうやってカレーを食べながら、自分はなんだかインドの神様のことがわかった気がしたんですよね。

マヒト:一神教みたいに一つの圧倒的な光を確定しておいたほうが、みんなを導きやすいというのはわかる。ただ、一つの神様がいてそこに全て依存する形でついていこうとするのって、だんだん余裕がなくなってくるんじゃないかなって思う。
多神教のようにたくさんの神様がいる世界って、真ん中からはずれた神様も許容していて、本来としか言えないけど日本も水の神様もいればトイレの神様もいる八百万の国じゃないですか。百個の神がいて百個の答えを提示してというのは健全だと思う。
映画の話に戻ると、はみ出てる人がいっぱいでてきたり、何回観ても話を回収しきれないっていうのは、そういう複雑さの肯定にもつながってくる。
映画の一つひとつのシーンも、登場人物も、それぞれが主役。主人公という意味では、富田健太郎演じるコウがいて、森山未來さんのヒー兄がいるんだけど。麻婆豆腐を食べるシーンには麻婆豆腐の時間がある。鉄板焼の上でジュワーって。


©STUDIO BLUE
佐内:あの麻婆豆腐、うまかったね。溢れ出してるよね。あのシーンには赤のバトンがあったから、赤でシーンをつないでる。富田(コウ)の時間、瑛太(久我)の時間、イチさんの時間。映画の中にそれぞれの時間が流れてる。
友だちと映画を観にいった帰り道に、喫茶店入って映画の話をしたりするじゃない。自分は映画のシーンの話はするんだけど、みんながあらすじの話をしてるときには「うん、うん」って頷いてるだけだったりする。映画の全体像はみえなくてもいいかなって。
マヒト:俺も佐内さんも、蛇口を開きっぱなしにしてそれを閉めるのを忘れて水中を楽しんでいるようなところがあって、説明をぶっ飛ばしているから、当然説明をもらえるのが当たり前っていう癖がついてる人はわかりにくいかもしれない。
以前、佐内さんから「ふわふわ食べいく?」って誘われて、一緒にパンケーキ食べにいったことがあるんです。それで車に乗ってお店に向かってるときに、「信号が赤になるときに、信号が『恋がしたい』って言うんだよね」って佐内さんが話してたのを覚えてます。だいたい言葉の使い方って、何かの目的を果たすために発するわけじゃないですか。そこがもう佐内さんの場合はエラーしているっていうか(笑)。
ストーリーに起承転結をつけていく方法もあると思うけど、たとえば自分がこうやって会話してるときにも、頭のどこかでまだインドのことを考えててワープしてしまう。アートとして見せたいとかではなくて、それくらい時系列もスキップしていくのって実は健全な状態だと思う。
佐内:そういう表現って必要だと思う。一つのことに留まってしまうと、奥行きが出てくる。奥に考えると争いがある世界に向かっちゃう。飛ぶことで争わない世界の可能性がそこにある気がして。部屋にずっといるわけじゃなくて、外に出て、知らないことを知って、明るくなる。話が飛んでいくっていうのは明るいし平和の可能性があるなって思う。

©STUDIO BLUE
映画や旅の遅さでしかアクセスできないもの。
―――マヒトさんの頭の中を映像化していくのに、ふたりはどうやって意思疎通していたのですか。脚本もマヒトさんが書かれていましたよね。
マヒト:脚本はあるけど、俺が現場に入って最初にする仕事は、役者よりなによりまず佐内さんに口頭でどう撮ってほしいかを伝えてましたね(笑)。口伝って大事だなと今回思った。
それこそアイヌのウポポ(歌)って、楽譜に落としちゃいけないんですよね。「フチ」ってアイヌ語で「おばあちゃん」のことを指すんですけど、それって神様を指す言葉でもあって「〜フチ」っていったりする。年齢を重ねるごとに神に近づいていく文化なんですよね。今、そんなフチ世代しか歌えない歌があって、次の世代に伝えるのに音符と歌詞を楽譜にしたらいいという話もあるんですけど、それでは伝承したことにならないといってアイヌの人たちは全部口伝で伝えようとしてるんです。そんなふうに口伝だけで映画撮る方法ってあるのかな。あったらおもしろいかもね。
映画って遅いメディアじゃないですか。観る側は、わざわざ映画館行って、席に2時間ホールドされて、はじめて向き合える。つくる側にしても、映画撮ってから劇場に流れるまでに『i ai』の場合は3年かかってるし。思ったことをすぐに言葉にできたり写真で表せるメディアに比べて、すごい時間がかかる。
その遅さって重要だと思っていて、どこか旅に近い。自分の身体をその場所まで運ぶって、効率的ではなくて、すごい遅い土地とのコミュニケーションじゃないですか。今、インターネットがあって、ケータイがあって、情報の速度もどんどん加速しているけど、たかだか人間が一日に感知できる情報や獲得できる量って限られてる。それをどこまで感じられるかが豊かさだと思うけど。映画や旅の遅さでしかアクセスできないことってあるんじゃないかな。

©STUDIO BLUE
マヒト:『i ai』では、コウがEコード引いたら、るり姉の部屋に飛んで最初にヒー兄からEコードを教わったシーンにつながる。時系列を越えて、音で飛んだり、色でつながったり、映画の強みを最大限まで使った気がする。
佐内:買い物とかもそうだよね。ネットでものを買うって、便利で時間が増えるような気がするけど、逆に時間がなくなってるんだなって思う。スーパーで買い物をすると、緑道を歩いて、甲州街道を通って、街路樹が風で揺れてるなとか、すれ違った人のことを感じているし、体力も使う。でもネットで買い物をするってことは、そうした時間がなくなることでもある。
写真は時間を止める仕事だから、時間ってなんだろうってよく考えるんだけど、時間って経験しないとなくなってしまうものなんだなって思う。
たとえばパソコンを開いてオンラインで打ち合わせをするのと、こうやって喫茶店で話をするのとも違うじゃない。ここにはコーヒーがあって、このカップとか灰皿とか水の配置も二度とないものだから。
マヒト:オンラインだと振動は共有できないですよね。自分は音の人だから、その違いを感じる。音って全部空気の振動じゃないですか。リモートだと情報と情報はもちろん交換できるんだけど、振動は絶対シェアできてない。やっぱりそれってコミュニケーションの純度が違ってくる。

故郷が増えていく。
―――『i ai』のHPに載っているマヒトさんの映画の制作日記のなかで、新神戸駅に降り立って街をロケハンしていて、「カットの構想が街に引っ張られてきられていく」ということを言っていましたね。マヒトさんにとって、明石や神戸はどういった場所なのでしょうか。
マヒト:コウやヒー兄が暮らしていた街は明石で撮っていたんだけど、撮影現場はなんにもない街。周りにコンビニもないし、工業地帯でもないし、道端でヤンキーが花火してるような。気の利いた店ができたら、江の島とか尾道みたいになりそうなんだけど、まだ発見される前の街という感じですね。
佐内:あがらない街。平熱の街。自分は、メインの街ではなくて途中の街がすごく好きで。映画を撮っていたあの場所は、どこまでいっても途中だった。そここそ日本を感じる。荻窪駅と西荻窪駅の間みたいなそういう場所って撮りやすいんですよね。カメラを持たないでいったら、ぼーっと時間が過ぎてしまうような。



©Masafumi Sanai
マヒト:この映画は旅のような気持ちでつくった部分はありますね。生まれたのは島根で、そのあと引っ越しをしていろんな場所に住んでいたから、これという地元がないんですよね。ずっと根なし草のような感覚があって、帰る場所がなくて行く場所だけがあるような。
ただ最近は行った場所が一個一個、故郷になっていってるのも感じます。『i ai』を撮影した明石も、映画にでてくる景色はやっぱりもう自分のなかで故郷化してるんですよね。
佐内:故郷って、遠くにいて思い出す場所のことなのかな。東京から離れて、NYに住んだら東京が故郷になるし。だからいろいろ故郷があるのは、自然なことだと思う。
マヒト:街とか景色が語りかけてくるのはありますね、絶対ね。やっぱり頭で考えてできるものもあるけど、それが完璧にはまるはずもないから。そこはやっぱり街の演出みたいなものが絶対かかわってくる。それは映画にかかわらずだと思うんですけど。
人があらゆることをコントロールできるとどこかで過信してるところがあるかもしれないけど、街なんて自分の思い通りにならないことで溢れてるじゃない。だから佐内さんが言っていたみたいに、部屋に閉じこもっていないで、窓が開いていて、街に出ていくのが大事なんじゃないかな。

©STUDIO BLUE
―――『i ai』には、ストーリーの本筋にかかわってくるかどうかわからない街の人たちが映画のなかに散りばめられていますよね。それがあの街だと、あの映画だと、とても自然なことのように映りました。
マヒト:ハナレグミの(永積)タカシさんが東京国際映画祭で『i ai』を観てくださったときに、「誰一人芝居してなかったね」って言ってくれて、その言葉はけっこううれしかったな。みんななんか自然とそこにいたっていう。もちろん基本的には脚本があって、台詞もあって、役者の経験値もさまざまなんだけど、なにか自然な形でそこに立っているドキュメンタリーともいえるようなものになってる。それだけみんなのなかにちゃんと神戸の海が流れていて、潮風を浴びていたんだと思う。

©STUDIO BLUE
マヒト:台詞を言わなきゃいけないんじゃなくて、言っているだけ。やらなきゃいけないんじゃなくて、やるだけっていうか。自分はどうしても監督としてその場にいるから、言葉の権限みたいのもいっぱいもってると思うけど、こうしてね、ああしてねっていうふうにコントロールしきりたくなくて。あたかもその人が選んだかのようにいてほしい。自分も揺さぶられようと思っていたし、役者一人ひとりも揺さぶられてほしいと思っていた。
佐内:みんな撮りやすかった。嘘つかずにストレートにカメラの中に入ってきて。それがちょっと寒かったりすると撮りにくくなってくるのかな? そういうのはなかった。
マヒト:ほとんど最初のカットを使ってましたしね。3回以上撮り直したシーンはなかったんじゃないかな。なんだったらもう「テスト本番!」っていって、それでいけるならそれでいっていたしね。
佐内:やっぱりライブだからさ。
マヒト:佐内さんが言っていた「寒くなる」という話でいうと、『i ai』にかかわった人たちがいたから、冷めずにできたんだなとも思う。たくさんの人がかかわる仕事って、波動を共有できなくなることもあるから、そういう意味では映画だって危ない面はあるはずなんだけど、自分の力というよりはそれは十三月(GEZANが主宰する音楽レーベル)のメンバーがいたから、健全なかたちで『i ai』がつくれた。
佐内:GEZANのメンバーが、撮影中の車止めしてくれたり、機材運ぶの手伝ってくれたりしていたもんね。
マヒト:「このシーンはカナブン越しで撮りたい!」っていって、虫取り網を買って朝から捕まえにいってくれたりね(笑)。

©STUDIO BLUE
生まれる前と死んだ後の時間を前借りする。
―――映画では、絵本のシーンがでてきたり、赤い服の集団がでてきたり、ホームレスのおじさんが言葉を投げかけてきたり、現実と幻想が入り交じるような場面がでてきますよね。そしてヒー兄自体も、現実とそうではない世界をぎりぎりのところで歩くような、ファンタジーのような存在のように感じました。
マヒト:この間、ライブでフィッシュマンズのゲストボーカルをしたんです。その時期は自分があまり調子がよくないときでもあったんですよね。一緒に音楽をやっていた仲間のオライビが死んでしまったのもあったから。
そんなときに、改めてフィッシュマンズの曲に深く潜ってみたんです。(ボーカル)佐藤さんが亡くなる前の最後のほうの曲を歌っていると、佐藤さんが考えていたことが流れ込んでくるような感覚があって。
佐藤さんがあちら側とこちら側の境界線をぱかぱかと点滅して跨いでいくようなところを、詩をなぞりながら感じていました。もう世界のことはどうでもよくなって、自分と彼女とふたりぼっちみたいな、ぐっと極端までクローズにするんだけど、ときどきみんなのことが気にかかって「調子はどうだい?」って外に問いかけたりして。フィッシュマンズの曲は、意識が最初にはじまったときから、どんどん線をまたぐことを怖がらなくなっていく歴史だと直感したんです。

©STUDIO BLUE
大体の人は死にたくないから、生きる理由を増やすことをしてる。週末遊びにいったり、おいしいごはん食べたり、自分の魂で仕事にかかわるとか......それってこの世界に踏みとどまる理由を探してるんだと思うんですよね。少なくとも俺はそうで、音楽も映画も、仕事の前にそんな活動としてやってるんですけど。
それがだんだん佐藤さんと一緒になって拡張していくと、この世界にとどまりたいというより、向こう側にいくことが怖くなくなっていく。この線より向こう側は想像していること、こちら側は現実に起きていることっていう境目がなくなって、自分の身体がのみ込まれていく。自分にもそういう点滅の感覚があるから、フィッシュマンズを歌いながら引っ張られるような感じがあったりして。

©STUDIO BLUE
マヒト:たとえば年をとって死に向かっていくときって、思い出だったり頭のなかで想像したことって曖昧になっていくと思うし、本当にあったかどうかってあんまり関係なくなっていくんじゃないかって。肉体がなくなったあとのファンタジーの世界に入っていって、土に還っていく準備をしている。逆にいうと赤ちゃんは無重力のところからやってくるもので。
だからヒー兄がファンタジーというのはそのとおりだと思うし、それと同時にそういうふうに向こう側とこちら側を行き来すること自体も健全なことなんじゃないかって思う。
もちろん佐藤さんが亡くなったことを寂しいと思う人もいっぱいいるだろうし、ヒー兄だってそう。でも俺からすると、現実とされてる世界のほうが、真実と真実の間の仮の時間のような気持ちがある。だって生まれてくる前と死んでいく後の間に挟まれた時間なわけですよね。現実のほうがなんか嘘っぽいんじゃないかって。佐内さんの写真とか詩とかも、そういう世界の感覚を前借りしてるんだと思うよ。

―――映画ではヒ―兄がいなくなった後の、コウやるり姉たちのそれぞれの時間も丁寧に描かれていますよね。そして一気にラストに向かっていく。
マヒト:ヒ―兄のいない世界を撮ることで、ある程度の翻訳としてのやさしさを残しています。
キラ(ヒー兄の弟)と子どもが絵本を読んでいるシーンで、ぱっと窓の外をみたときに造花の花が咲いていたり、その赤い花が風で運ばれてライブハウスに落ちていたり......。そうやって身体が亡くなっても、別のものに置き換わったり、誰かの意志として残ったりして、生かすことができる。
マヒト:それってつくるものにもいえることで、佐内さんの写真集だってその写真の被写体も写真のなかで永遠に生きてるじゃないですか。
いろんなかたちで自分のドッペルゲンガーみたいなもうひとつの私を細かく刻んで、置いていってるんだと思う。こうやって会話していても、相手のなかに自分の存在を置いてきたり、その人の記憶に自分の住所をつくって、故郷をつくってしまうことを、みんな自然とやっているんですよね。

INFORMATION
『i ai』
兵庫の明石。期待も未来もなく、単調な日々を過ごしていた若者・コウ(富田健太郎)の前に、地元で有名なバンドマン・ヒー兄(森山未來)が現れる。ヒー兄に憧れてバンドをはじめたコウは、仲間に囲まれて音楽をする日々を送っていた。そんなとき、メジャーデビューを目前にしていたヒー兄と突然の別れが訪れるーーー。監督・脚本・音楽:マヒトゥ・ザ・ピーポー
富田健太郎、森山未來、さとうほなみ、堀家一希、永山瑛太、小泉今日子、吹越満、大宮イチ
撮影:佐内正史
劇中画:新井英樹
製作プロダクション:スタジオブルー
配給:パルコ
https://i-ai.jp/

PROFILE
マヒトゥ・ザ・ピーポー●2009年に大阪で「GEZAN」を結成。作詞作曲を担当、ボーカルとして音楽活動をする。音楽レーベル「十三月」を主宰。青葉市子とのユニット「NUUAMM」やソロ活動もおこなう。小説『銀河で一番静かな革命』、エッセイ『ひかりぼっち』を出版。豊田利晃監督の劇映画『破壊の日』に出演。
IG|mahitothepeople_gezan
佐内正史(さない・まさふみ)●1997年に写真集『生きている』でデビュー。写真集『MAP』で木村伊兵衛写真賞を受賞。独自レーベル「対照」を立ち上げて写真集を発表しつづけている。最新刊に『写真の体毛』『静岡詩』等。曽我部恵一とのユニット「擬態屋」では、佐内の詩と曽我部の音合わせをした作品を発表している。
IG|@sanaimasafumi
IG|mahitothepeople_gezan
佐内正史(さない・まさふみ)●1997年に写真集『生きている』でデビュー。写真集『MAP』で木村伊兵衛写真賞を受賞。独自レーベル「対照」を立ち上げて写真集を発表しつづけている。最新刊に『写真の体毛』『静岡詩』等。曽我部恵一とのユニット「擬態屋」では、佐内の詩と曽我部の音合わせをした作品を発表している。
IG|@sanaimasafumi