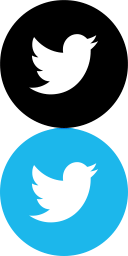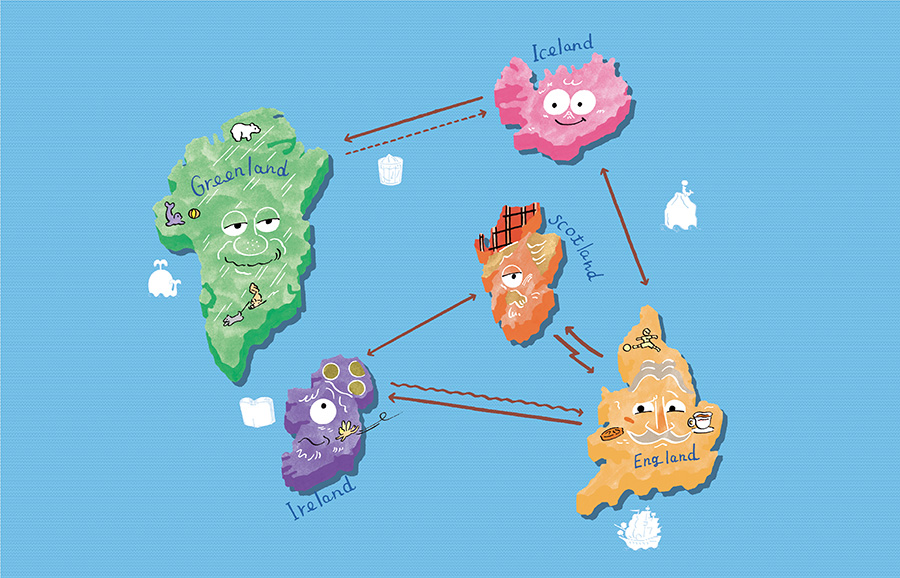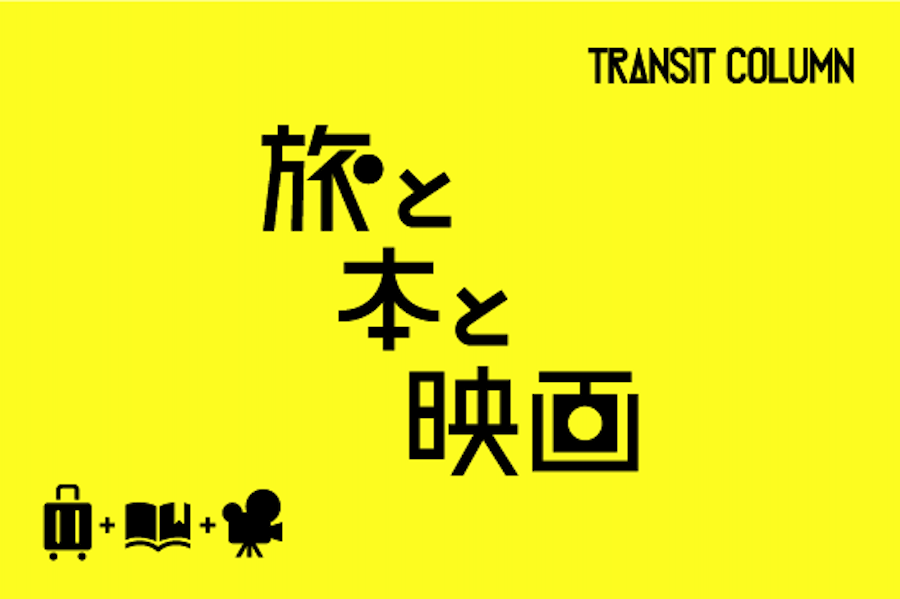旅と本と映画
アイスランドを知る5作
朱位昌併選
本や映画で世界を旅しよう。
そのエリアに造詣の深い方々を案内人とし、作品を教えていただく連載の第10回。
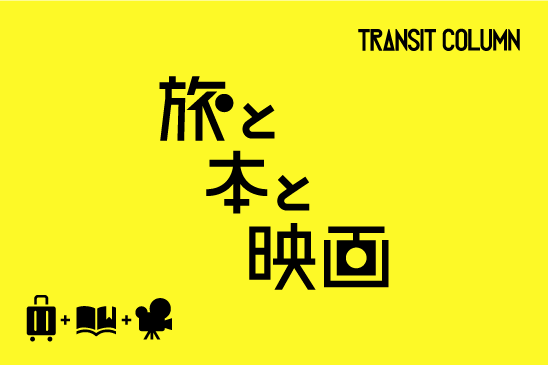
福祉や男女平等などの進歩的政策や、最近は火山の爆発で話題となったアイスランド。
トピック豊富な小さな北の島国を、もう一段深く知るための5作品を、アイスランド文学研究者の朱位昌併さんに選んでもらいました。
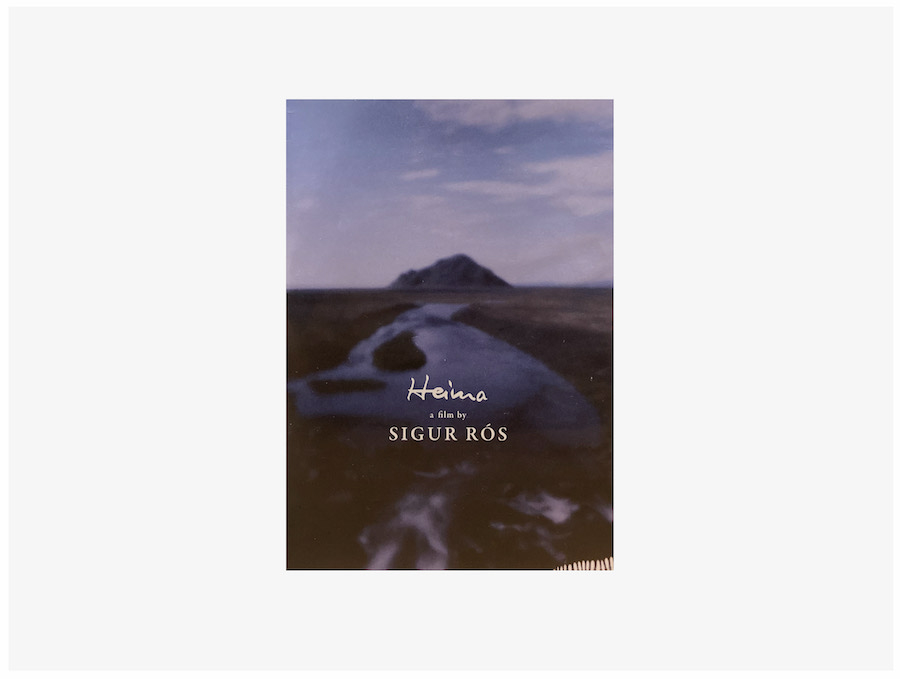
冬のアイスランドにやってきて、地平線を低く移動する太陽が沈む寸前に放つ赤々しさや、そのあとにつづく夜の長さに驚く人は少なくない。昼は明るく夜は暗い地域に生まれ育ったことを幸いに思う人もいれば、灼々とした日の入りに神々の黄昏と呼ばれる北欧神話の終末を重ね合わせる人もいる。一方でふと、白夜のアイスランドが気になってくるかもしれない。日が沈まない季節の夜はどのようなものなのか、と。
シガー・ロスが2006年夏に地元アイスランドで行ったツアーの模様を収めた『Heima』には、白夜のアイスランドの静謐さが詰まっている。アイスランド各地で行われたコンサート映像には、この国の小さな首都圏の外に延々と広がる自然はもちろん、その傍らで暮らす人びとの賑わいが収められている。
とくにバンドメンバーが「特別だった」と語るアウスビルギ(Ásbyrgi)でのコンサートが秀逸だ。空に茜色を落とすだけで真っ暗闇になることがない夏の夜のアイスランドで行われた野外公演を大音量で流していると、耳のなかで小さく鳴りつづけるせせらぎのような、何かが絶えず微動している白夜の静寂が感じられる。明るい夜の平原で、頭を空っぽにして座っているだけのような、特別な時間である。
ここから購入・視聴可能

火口から地球内部へと下りていき、そこに広がる未知の世界を目の当たりにする鉱物学者リーデンブロック教授たちの冒険を初めて読んだのはいつだったか憶えていないが、文字を追っていただけに違いない。その火口がアイスランドにあることをまったく記憶していなかったのだから。
19世紀中頃に刊行された本作で描かれるアイスランドの様子は、現在のものとはずいぶん違う。首都レイキャヴィークには通りが2本しかなく、3時間もあれば町の周辺も含め、すべてを歩いて見終えてしまえるらしい。フランスの作家ジュール・ヴェルヌの描くアイスランドには、かつては確かにそうだったろうし、今でもそうであるといえるところもあれば、誇張されているところ、明らかに事実でないところもあるが、現地を訪れることなく資料と想像力を頼りに書き上げた彼の筆致は驚くべきものだ。
幼い頃とは反対に、地球の内部へ下りていくまでの、とりわけアイスランドに関わる部分を熱心に読んでからというもの、山岳地を散策したり乗馬をするたびに『地底旅行』を想起して、つい口元が緩んでしまう。地質学的には若いこの土地に、人の営みよりはるかに時を重ねたものどもの気配が濃厚にあることを、ヴェルヌは海の向こうから感じ取っていたのだろうか。


アイスランド各地の町や村をつなぐ道中の平地や山裾のところどころに、農家が点在している。本当に人がいるのかと訝しんでしまうが、そういった場所で暮らす人びとのことが気になったら、映画『ひつじ村の兄弟』を観てほしい。
アイスランド北部の人里離れた地域に、40年もの間ほとんど互いに口をきいていない二人の老兄弟が住んでいる。ともに優れた羊農家であるが、ある日、兄の羊がスクレイピーという疫病に罹ってしまう。保健所は、集落すべての羊の殺処分に加え、感染源となりうる干し草などもすべて処分する必要があり、その土地で新たに羊を飼えるのは2年後だと告げる。生活のほぼすべてを羊に捧げてきた人びとには、ひどく残酷な通告だ。
自分の意思とは無関係にそれまでの生活を捨てざるを得ない状況は、はた目には滑稽な行為に人を駆り立てうる。どうやってこんなところで、そうまでしてなぜ、とアイスランドを旅して回ると浮かんでくる好奇や疑問の直接の答えにはならないとしても、本作を観ると、風景の一部だった農家には、代々家畜を愛し、誇りをもって己のすべてを捧げる人が住んでいるのかもしれない、と背筋を伸ばしたくなる。映画を観た後、夕食にラム肉を買った。オーブンで焼いた300gのブロック肉に敬意を払い、平らげた。
 夏になるとアイスランドにやって来るキョクアジサシが、フランスの首都パリに嵐雲のように現れた。ここから始まる世界の異変の原因は、電場や通信、信号で世界が飽和状態になったことだった。アイスランドのラブスター博士率いる科学者集団によって無事に異変は解決されるが、彼らの発明ですっかり様変わりした世界は、可笑しみはあれど不気味である。
夏になるとアイスランドにやって来るキョクアジサシが、フランスの首都パリに嵐雲のように現れた。ここから始まる世界の異変の原因は、電場や通信、信号で世界が飽和状態になったことだった。アイスランドのラブスター博士率いる科学者集団によって無事に異変は解決されるが、彼らの発明ですっかり様変わりした世界は、可笑しみはあれど不気味である。
土産物屋でぬいぐるみが大人気の渡り鳥パフィンは、もはや野生ではなく、厳しい観光客の要求に応えるように改良され、工場で生産されている。七色のくちばしを持ち、実に美味らしいその鳥は、「私を食べて、私を食べて!」と歌うのだ。アイスランドらしい(?)皮肉の効いたユーモアが散りばめられている本書では、現実と薄皮一枚挟んだ現実の向こう側のアイスランドを旅することができるだろう。
物語は全世界を巻き込み展開するが、19世紀に自国で書かれた小説や詩を下敷きにする本書の根っこは、しっかりアイスランドにある。ローカルなものを狭く深く掘りつづけていけば、いずれは遍く通じるものに達する。そう信じる作家の手掛けたSF小説で浮かび上がる北欧の島国は、極東の島国からすると異世界めいているかもしれないが、どこか身近に感じるところもあるはずだ。

ガイドとともにアイスランドを巡っていると、「ここは、中世の頃~」と始まる話をきっと何度も耳にする。また、アイスランドの本を読めば、中世に書き残されたサガと呼ばれる散文群に立脚するものにしょっちゅう出くわすことだろう。アイスランドを語るうえで避けて通れない中世に興味があるなら、サガを読まない理由はない。
本書には、とりわけ有名なサガの邦訳が収められており、植民の時代やキリスト教に改宗する前後のことなど、今なお語り草である出来事がどのように書き残されたのか、その一端を伺い知れる。現代からすると破格なことばかり起こって目を剥くかもしれないが、アイスランドの人びとは、そういった話を語り継ぎ、語り直しながら現在の歴史や文化をつくってきた。
彼らが原点とするものがなにか、ページをめくってもよく分からないかもしれないが、それまでとは違う印象をアイスランドに抱くだろう。ただ、あまり中世を偏重すると、サッカーやハンドボールなどの試合で熱狂するアイスランド人を前にして、「この猛々しさはヴァイキングの名残だろうか」と筆者のように安直に重ね合わせたくなるかもしれないので、少し注意が必要だ。
残念ながら本書は現在絶版であるが、近いうちに復刊されることを願っている。
朱位昌併(あかくら・しょうへい)●アイスランド在住。詩人、翻訳家、アイスランド文学研究者。単訳書にラニ・ヤマモト著『さむがりやのスティーナ』(平凡社)。
そのエリアに造詣の深い方々を案内人とし、作品を教えていただく連載の第10回。
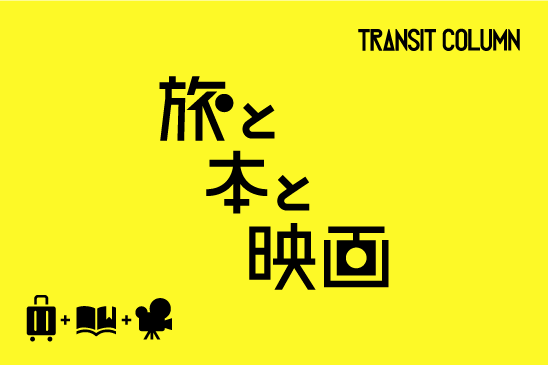
福祉や男女平等などの進歩的政策や、最近は火山の爆発で話題となったアイスランド。
トピック豊富な小さな北の島国を、もう一段深く知るための5作品を、アイスランド文学研究者の朱位昌併さんに選んでもらいました。
アイスランドを知る本と映画
text=SHOHEI AKAKURA
『Heima』
ディーン・デュボア監督
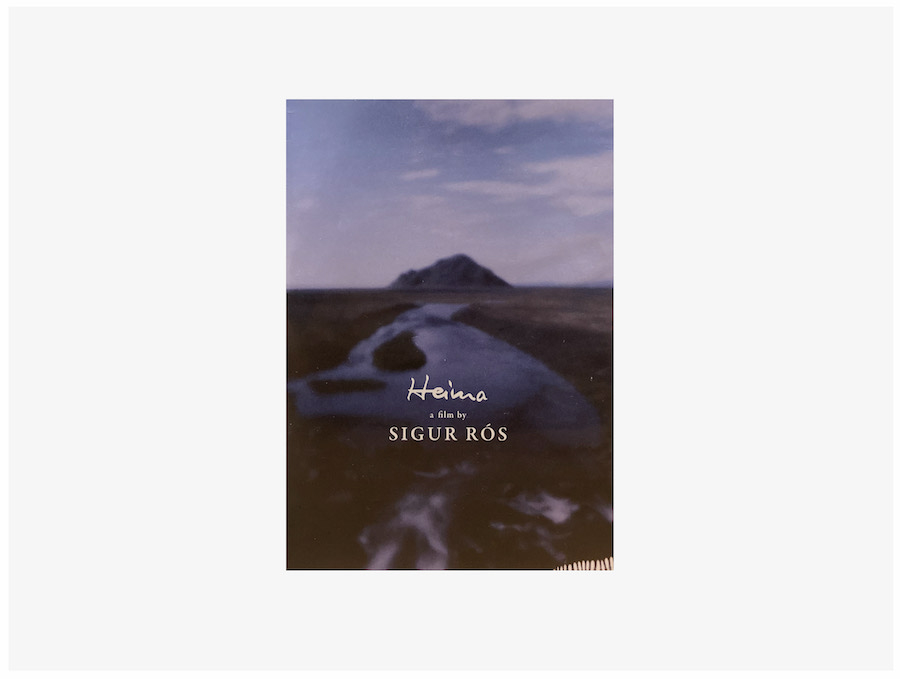
冬のアイスランドにやってきて、地平線を低く移動する太陽が沈む寸前に放つ赤々しさや、そのあとにつづく夜の長さに驚く人は少なくない。昼は明るく夜は暗い地域に生まれ育ったことを幸いに思う人もいれば、灼々とした日の入りに神々の黄昏と呼ばれる北欧神話の終末を重ね合わせる人もいる。一方でふと、白夜のアイスランドが気になってくるかもしれない。日が沈まない季節の夜はどのようなものなのか、と。
シガー・ロスが2006年夏に地元アイスランドで行ったツアーの模様を収めた『Heima』には、白夜のアイスランドの静謐さが詰まっている。アイスランド各地で行われたコンサート映像には、この国の小さな首都圏の外に延々と広がる自然はもちろん、その傍らで暮らす人びとの賑わいが収められている。
とくにバンドメンバーが「特別だった」と語るアウスビルギ(Ásbyrgi)でのコンサートが秀逸だ。空に茜色を落とすだけで真っ暗闇になることがない夏の夜のアイスランドで行われた野外公演を大音量で流していると、耳のなかで小さく鳴りつづけるせせらぎのような、何かが絶えず微動している白夜の静寂が感じられる。明るい夜の平原で、頭を空っぽにして座っているだけのような、特別な時間である。
ここから購入・視聴可能
『地底旅行』
ジュール・ヴェルヌ著、朝比奈弘治訳(岩波文庫)

火口から地球内部へと下りていき、そこに広がる未知の世界を目の当たりにする鉱物学者リーデンブロック教授たちの冒険を初めて読んだのはいつだったか憶えていないが、文字を追っていただけに違いない。その火口がアイスランドにあることをまったく記憶していなかったのだから。
19世紀中頃に刊行された本作で描かれるアイスランドの様子は、現在のものとはずいぶん違う。首都レイキャヴィークには通りが2本しかなく、3時間もあれば町の周辺も含め、すべてを歩いて見終えてしまえるらしい。フランスの作家ジュール・ヴェルヌの描くアイスランドには、かつては確かにそうだったろうし、今でもそうであるといえるところもあれば、誇張されているところ、明らかに事実でないところもあるが、現地を訪れることなく資料と想像力を頼りに書き上げた彼の筆致は驚くべきものだ。
幼い頃とは反対に、地球の内部へ下りていくまでの、とりわけアイスランドに関わる部分を熱心に読んでからというもの、山岳地を散策したり乗馬をするたびに『地底旅行』を想起して、つい口元が緩んでしまう。地質学的には若いこの土地に、人の営みよりはるかに時を重ねたものどもの気配が濃厚にあることを、ヴェルヌは海の向こうから感じ取っていたのだろうか。
『ひつじ村の兄弟』
グリームル・ハウコナルソン監督


アイスランド各地の町や村をつなぐ道中の平地や山裾のところどころに、農家が点在している。本当に人がいるのかと訝しんでしまうが、そういった場所で暮らす人びとのことが気になったら、映画『ひつじ村の兄弟』を観てほしい。
アイスランド北部の人里離れた地域に、40年もの間ほとんど互いに口をきいていない二人の老兄弟が住んでいる。ともに優れた羊農家であるが、ある日、兄の羊がスクレイピーという疫病に罹ってしまう。保健所は、集落すべての羊の殺処分に加え、感染源となりうる干し草などもすべて処分する必要があり、その土地で新たに羊を飼えるのは2年後だと告げる。生活のほぼすべてを羊に捧げてきた人びとには、ひどく残酷な通告だ。
自分の意思とは無関係にそれまでの生活を捨てざるを得ない状況は、はた目には滑稽な行為に人を駆り立てうる。どうやってこんなところで、そうまでしてなぜ、とアイスランドを旅して回ると浮かんでくる好奇や疑問の直接の答えにはならないとしても、本作を観ると、風景の一部だった農家には、代々家畜を愛し、誇りをもって己のすべてを捧げる人が住んでいるのかもしれない、と背筋を伸ばしたくなる。映画を観た後、夕食にラム肉を買った。オーブンで焼いた300gのブロック肉に敬意を払い、平らげた。

『ラブスター博士の最後の発見』
アンドリ・スナイル・マグナソン著、佐田千織訳(東京創元社)
 夏になるとアイスランドにやって来るキョクアジサシが、フランスの首都パリに嵐雲のように現れた。ここから始まる世界の異変の原因は、電場や通信、信号で世界が飽和状態になったことだった。アイスランドのラブスター博士率いる科学者集団によって無事に異変は解決されるが、彼らの発明ですっかり様変わりした世界は、可笑しみはあれど不気味である。
夏になるとアイスランドにやって来るキョクアジサシが、フランスの首都パリに嵐雲のように現れた。ここから始まる世界の異変の原因は、電場や通信、信号で世界が飽和状態になったことだった。アイスランドのラブスター博士率いる科学者集団によって無事に異変は解決されるが、彼らの発明ですっかり様変わりした世界は、可笑しみはあれど不気味である。
土産物屋でぬいぐるみが大人気の渡り鳥パフィンは、もはや野生ではなく、厳しい観光客の要求に応えるように改良され、工場で生産されている。七色のくちばしを持ち、実に美味らしいその鳥は、「私を食べて、私を食べて!」と歌うのだ。アイスランドらしい(?)皮肉の効いたユーモアが散りばめられている本書では、現実と薄皮一枚挟んだ現実の向こう側のアイスランドを旅することができるだろう。
物語は全世界を巻き込み展開するが、19世紀に自国で書かれた小説や詩を下敷きにする本書の根っこは、しっかりアイスランドにある。ローカルなものを狭く深く掘りつづけていけば、いずれは遍く通じるものに達する。そう信じる作家の手掛けたSF小説で浮かび上がる北欧の島国は、極東の島国からすると異世界めいているかもしれないが、どこか身近に感じるところもあるはずだ。
『アイスランド サガ』
谷口幸男訳(絶版)

ガイドとともにアイスランドを巡っていると、「ここは、中世の頃~」と始まる話をきっと何度も耳にする。また、アイスランドの本を読めば、中世に書き残されたサガと呼ばれる散文群に立脚するものにしょっちゅう出くわすことだろう。アイスランドを語るうえで避けて通れない中世に興味があるなら、サガを読まない理由はない。
本書には、とりわけ有名なサガの邦訳が収められており、植民の時代やキリスト教に改宗する前後のことなど、今なお語り草である出来事がどのように書き残されたのか、その一端を伺い知れる。現代からすると破格なことばかり起こって目を剥くかもしれないが、アイスランドの人びとは、そういった話を語り継ぎ、語り直しながら現在の歴史や文化をつくってきた。
彼らが原点とするものがなにか、ページをめくってもよく分からないかもしれないが、それまでとは違う印象をアイスランドに抱くだろう。ただ、あまり中世を偏重すると、サッカーやハンドボールなどの試合で熱狂するアイスランド人を前にして、「この猛々しさはヴァイキングの名残だろうか」と筆者のように安直に重ね合わせたくなるかもしれないので、少し注意が必要だ。
残念ながら本書は現在絶版であるが、近いうちに復刊されることを願っている。
朱位昌併(あかくら・しょうへい)●アイスランド在住。詩人、翻訳家、アイスランド文学研究者。単訳書にラニ・ヤマモト著『さむがりやのスティーナ』(平凡社)。