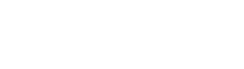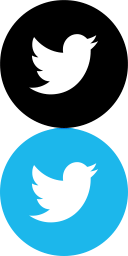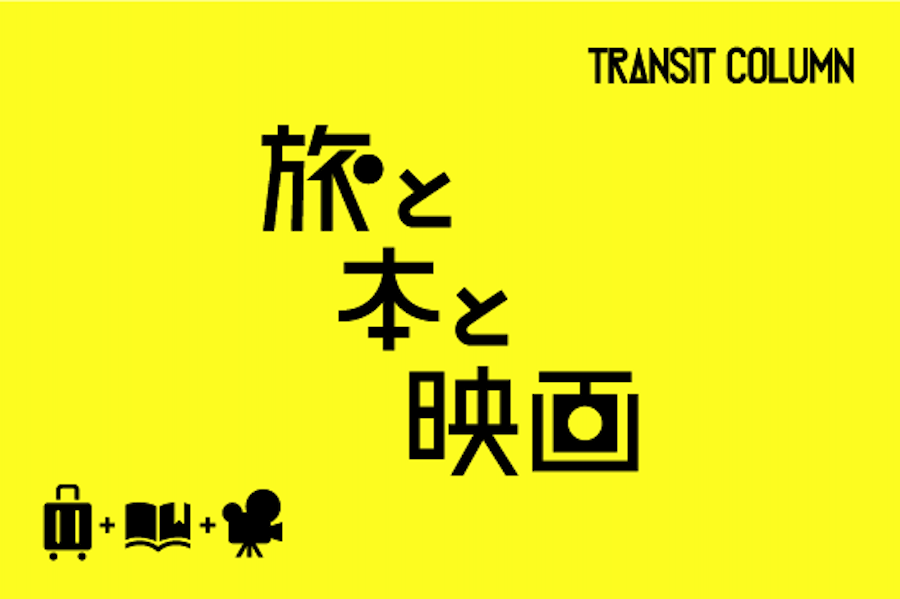旅と本と映画
ウクライナを知る5作
梶山祐治選
本や映画で世界を旅しよう。
そのエリアに造詣の深い方々を案内人とし、作品を教えていただく連載の第7回目。
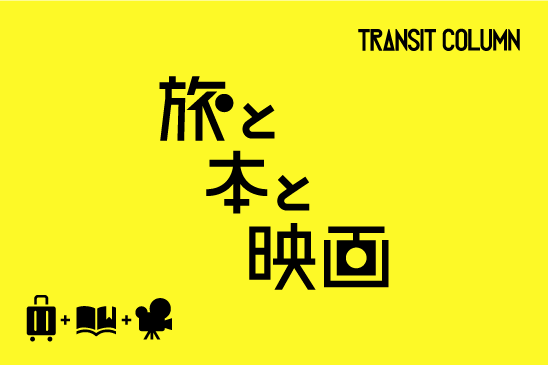
一つの作品が、それまで知らなかった世界を開いてくれることもある。物語は、その国の美しさや悲しさを垣間見ることのできる貴重な機会をくれる。今回はウクライナの文学、映画に詳しい梶山祐治さんに選んでいただきました。
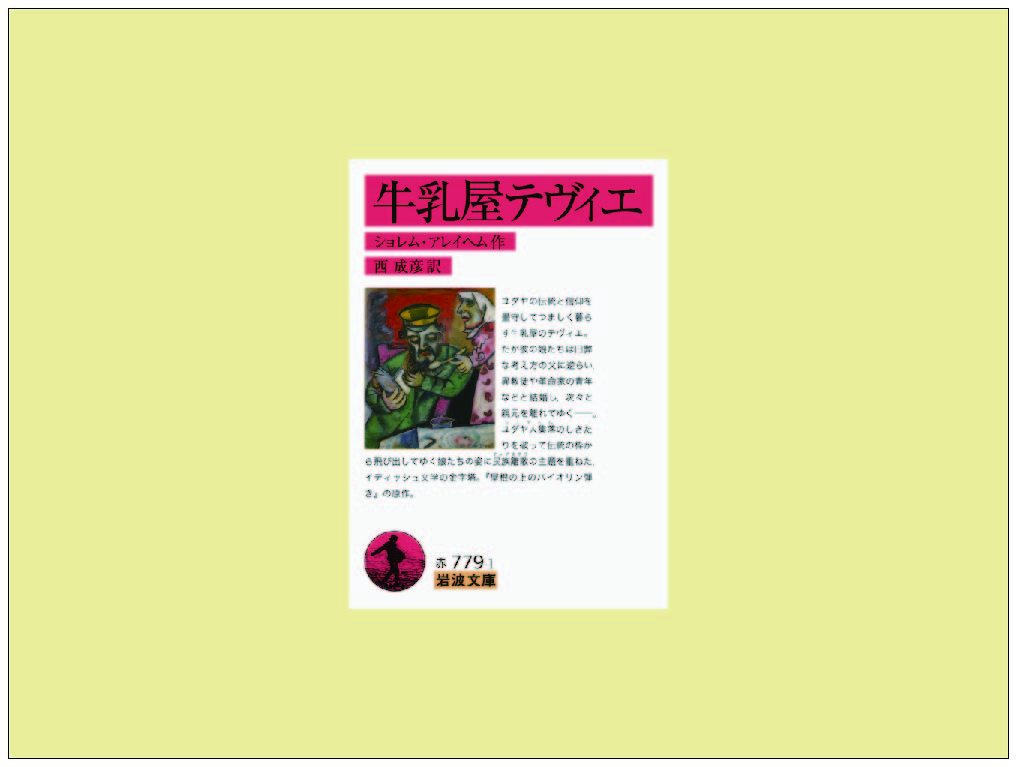 「ショレム・アレイヘム」とは、東欧のユダヤ人が話す言語イディッシュ語で「あなたに平和を」といった意味の日常的な挨拶の言葉であり、ロシア帝政下のウクライナに生まれたユダヤ人のシャロム・ラビノヴィッチがイディッシュ語での執筆時に用いたペンネームである。イディッシュ文学の第一人者であるアレイヘムの代表作がこの『牛乳屋テヴィエ』だ。19世紀末から20世紀初めにかけて連作短編として書かれ、ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』の原作としてもよく知られている。
「ショレム・アレイヘム」とは、東欧のユダヤ人が話す言語イディッシュ語で「あなたに平和を」といった意味の日常的な挨拶の言葉であり、ロシア帝政下のウクライナに生まれたユダヤ人のシャロム・ラビノヴィッチがイディッシュ語での執筆時に用いたペンネームである。イディッシュ文学の第一人者であるアレイヘムの代表作がこの『牛乳屋テヴィエ』だ。19世紀末から20世紀初めにかけて連作短編として書かれ、ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』の原作としてもよく知られている。
ユダヤの信仰に忠実な牛乳屋のテヴィエは、年頃の娘たちをたくさん抱えている。父親は娘を裕福なユダヤ人に嫁がせることを望んでいるが、時は社会が著しく変化を遂げている世紀の変わり目である。娘たちは父の考え方に逆らうようにして、異教徒や革命運動に身を捧げる青年たちと次々に結婚して親元を離れてゆく。当時の多民族文化を反映して、作品にヘブライ語やアラム語、ロシア語・ウクライナ語といったスラヴ語も登場する。
小説の書かれた当時と比べ、ポグロム(ユダヤ人襲撃)やホロコースト、イスラエルへの移住によって現在のウクライナのユダヤ人は著しく減少したが、同国に根づくユダヤ文化を知ることのできる1冊である。
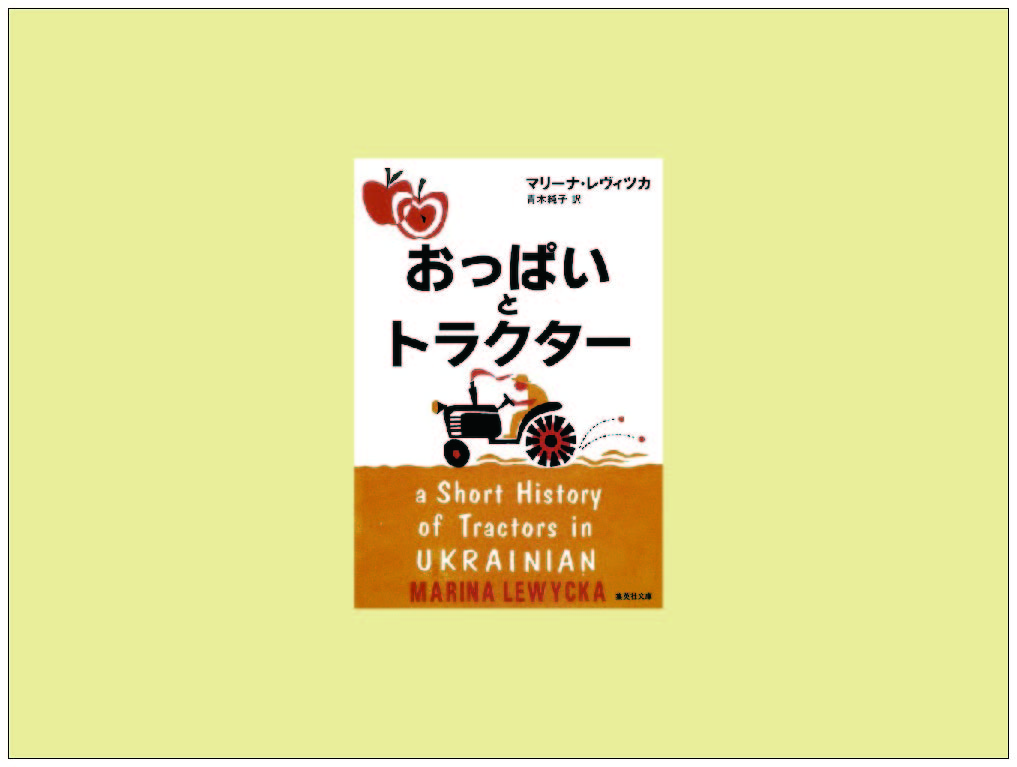 原題を『ウクライナ語版トラクター小史 A Short History of Tractors in Ukrainian』というこの小説は、イギリスで暮らすウクライナ系移民一家に突然湧き起こった家族騒動を描いている。物語は、主人公ナージャの84歳になる父親が、36歳の豊満な肉体を持つウクライナ人女性ヴァレンチナと結婚すると言い出すところから始まる。ウクライナ出身のニコライは元トラクターの技師で、ヴァレンチナは彼と結婚して財産とイギリスのパスポートを手に入れようとしている。そこでナージャは母親の遺産をめぐって骨肉の争いをしていた姉と一時休戦し、父親を守るための共闘を開始するのだった。
原題を『ウクライナ語版トラクター小史 A Short History of Tractors in Ukrainian』というこの小説は、イギリスで暮らすウクライナ系移民一家に突然湧き起こった家族騒動を描いている。物語は、主人公ナージャの84歳になる父親が、36歳の豊満な肉体を持つウクライナ人女性ヴァレンチナと結婚すると言い出すところから始まる。ウクライナ出身のニコライは元トラクターの技師で、ヴァレンチナは彼と結婚して財産とイギリスのパスポートを手に入れようとしている。そこでナージャは母親の遺産をめぐって骨肉の争いをしていた姉と一時休戦し、父親を守るための共闘を開始するのだった。
著者のレヴィツカは、ドイツ・キールの難民キャンプでウクライナ出身の両親のもとに生まれたウクライナ系イギリス人で、ニコライは彼女の父をモデルにしている。ニコライの口や家族会議で飛び出す話から、ニコライたちが飢饉(後述の『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』を参照)と独ソ戦を生き延びるためどれほど必死に生きてきたか、ナージャの知らなかった真実が浮かび上がってくる。彼を救ったのは、ヨーロッパ有数の穀倉地帯で身につけたトラクター技師としての腕だった。
その受難の歴史を知ったとき、祖国からやって来た若い女性を前にしたニコライの舞い上がりぶりを、読者は単純には断罪できないのではないだろうか。ヴァレンチナが飢えとは無縁な肉体を誇っていることも重要だろう。


『火の馬』(原題『忘れられた祖先の影』)は、ウクライナの国立映画機関である国立オレクサンドル・ドヴジェンコ映画センターが2021年に選出したウクライナ映画のオール・タイム・ベストにおいて、センターにその名が冠せられているドヴジェンコ監督の代表作『大地』(1930)を抑え、堂々の1位に輝いた作品である。
監督はジョージア生まれのアルメニア人であるセルゲイ・パラジャーノフで、全編ウクライナ語で製作された。世界映画史に燦然とその名を輝かせるこの映画作家は、ウクライナとの縁が深かった。全ソ国立映画大学ではドヴジェンコらに師事し、フィルモグラフィ前半の作品のほとんどがキエフにあるドヴジェンコ記念映画スタジオで制作されている。
そしてウクライナでの映画制作の頂点とされるのが、西部のカルパティア山脈を舞台に、反目しあう一家同士の幼なじみイヴァンとマリーチカの悲恋を色彩豊かに描いた『火の馬』である。マリーチカが命を落とした後にモノクロに切り替わる瞬間は、それまでの映像が鮮やかなだけに、主人公の沈んだ心を表して痛々しい。この作品で世界的にも認知されたパラジャーノフは、次作でその先鋭化した映像を批判され、アルメニアへと拠点を移すのだった。


1933年、世界恐慌の只中にソ連だけが好景気であることに疑問を抱いたイギリス人ジャーナリストのガレス・ジョーンズは、決死の潜入取材を敢行し、秘密があるというウクライナへ向かう。そこで彼が目にするのは、ソ連指導部が粉飾して見せるうわべの景気とはあまりにかけ離れた、目を覆うばかりの光景だった。ポーランドの映画監督アグニェシュカ・ホランドが実話に基づいて撮った『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』は、当時のウクライナ国内の様子をよく知ることができる作品である。
ソ連時代のウクライナでは、旱魃や戦争、政府による強制的な穀物調達といった理由から、1920年代、30年代、40年代にそれぞれ大規模な飢饉が3度発生した。このうち、1932〜33年に起きた飢饉は、1929年に始まったソヴィエト政権下の農業集団化の過程で、富農の追放や政府による強制的な穀物調達などが原因であった。ウクライナでは「飢餓」を意味する「ホロド」と「疫病」を表す「モール」を合わせて「ホロドモール」と呼ばれ、とくに多くの被害者を生んだ。前出の『おっぱいとトラクター』の元トラクター技師ニコライは、この飢饉が農業集団化に抵抗した農民たちへのスターリンの報復だったと信じていた。ホロドモールがソ連政府によるウクライナ人を狙い撃ちしたものという説は現在は研究者によって否定されているが、人為的要因によって被害が拡大したこの悲劇がウクライナ人に与えた傷の大きさを想像させてやまない。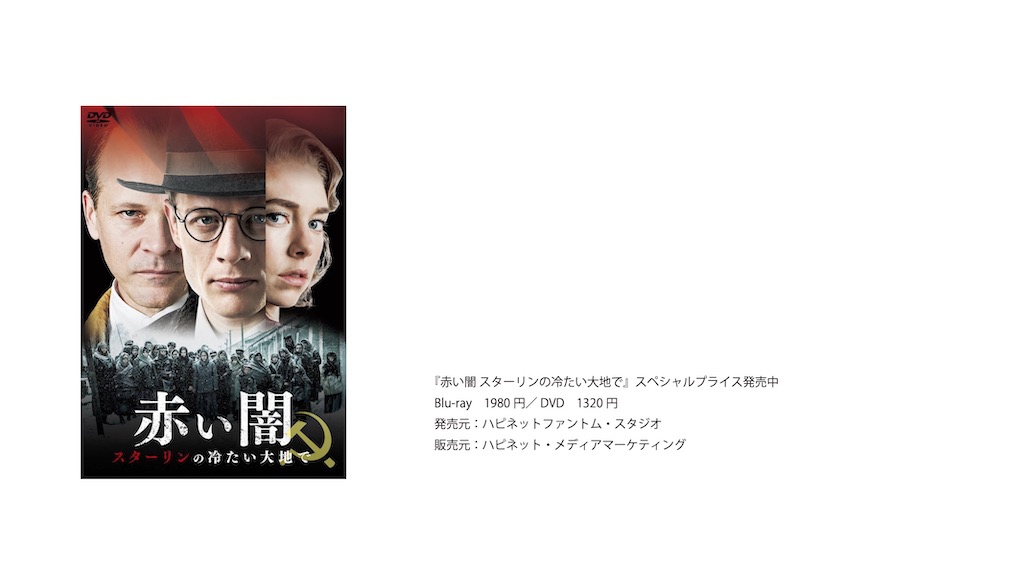


映画はキエフにあるオペラハウスの戦闘シーンで幕を開ける。銃撃戦の原因となっているのがプルトニウム241であることに、1986年にチェルノブイリで起きた原発事故との連想が働いていることは間違いない。2020年に公開されたこの映画の背景には、2014年に起きたロシアによるクリミア併合や東部ドンバスでの紛争を経て、ハリウッドを中心とする欧米の映画作品でウクライナが危険な場所として全世界の観客に提示されるようになってしまった側面がある。
サイモン・ウェスト監督の『コードネーム:ストラットン』(2017)では、元ロシアの諜報機関のスパイがイランで入手した生物兵器を、最初にウクライナで使用していた。フェデ・アルバレスの『蜘蛛の巣を払う女』(2018)では、主人公の天才ハッカーを追うアメリカの諜報機関に所属するセキュリティ専門家が、アフガニスタンやウクライナに駐留していたことが肩書きとして観客に紹介される。
『TENET テネット』もまた、こうした「危険なウクライナ」を提示する作品の系譜に連なっている。ヴィットリオ・デ・シーカの往年の戦後ドラマ『ひまわり』(1970)が映す、長閑な農村の風景と現在のハリウッドが描くウクライナとは、隔世の感がある。地平線の彼方まで続いていたひまわり畑のような長閑なウクライナの風景は、再びいつ映画に登場するだろうか。
梶山祐治(かじやま・ゆうじ)●筑波大学国際局グローバル・コモンズUIA。東京大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。専門はロシア文学・映画。中央アジア今昔映画祭やオンラインによるロシア・中央アジア上映会などで日本未公開作品の紹介を続けている。論文に「中央アジア映画史への招待」『中央アジア今昔映画祭パンフレット』(トレノバ、2021)など。
そのエリアに造詣の深い方々を案内人とし、作品を教えていただく連載の第7回目。
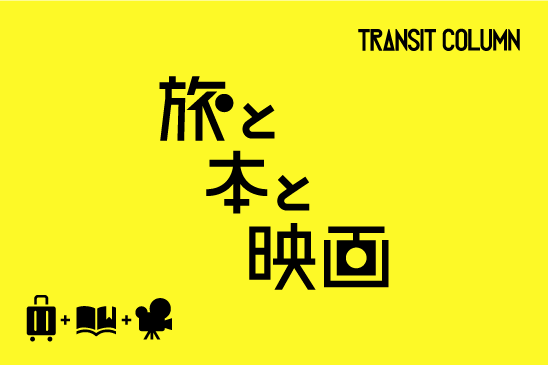
一つの作品が、それまで知らなかった世界を開いてくれることもある。物語は、その国の美しさや悲しさを垣間見ることのできる貴重な機会をくれる。今回はウクライナの文学、映画に詳しい梶山祐治さんに選んでいただきました。
ウクライナを知る5つの本と映画
text=YUJI KAJIYAMA
『牛乳屋テヴィエ』
ショレム・アレイヘム著、西成彦訳(岩波文庫)
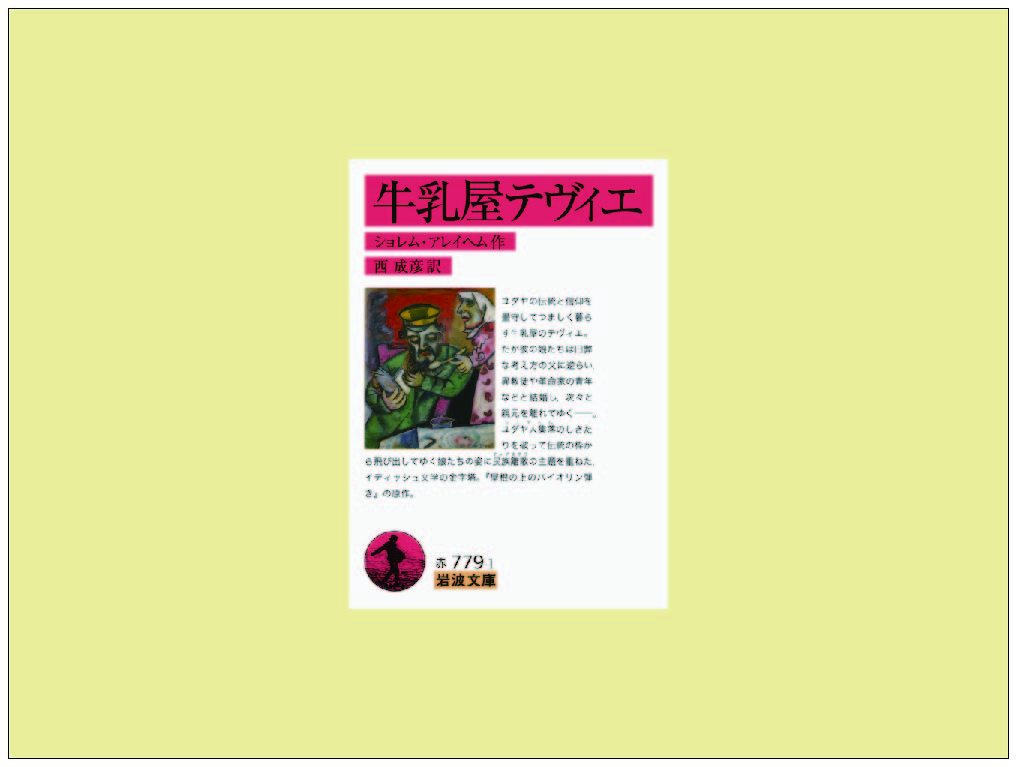 「ショレム・アレイヘム」とは、東欧のユダヤ人が話す言語イディッシュ語で「あなたに平和を」といった意味の日常的な挨拶の言葉であり、ロシア帝政下のウクライナに生まれたユダヤ人のシャロム・ラビノヴィッチがイディッシュ語での執筆時に用いたペンネームである。イディッシュ文学の第一人者であるアレイヘムの代表作がこの『牛乳屋テヴィエ』だ。19世紀末から20世紀初めにかけて連作短編として書かれ、ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』の原作としてもよく知られている。
「ショレム・アレイヘム」とは、東欧のユダヤ人が話す言語イディッシュ語で「あなたに平和を」といった意味の日常的な挨拶の言葉であり、ロシア帝政下のウクライナに生まれたユダヤ人のシャロム・ラビノヴィッチがイディッシュ語での執筆時に用いたペンネームである。イディッシュ文学の第一人者であるアレイヘムの代表作がこの『牛乳屋テヴィエ』だ。19世紀末から20世紀初めにかけて連作短編として書かれ、ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』の原作としてもよく知られている。ユダヤの信仰に忠実な牛乳屋のテヴィエは、年頃の娘たちをたくさん抱えている。父親は娘を裕福なユダヤ人に嫁がせることを望んでいるが、時は社会が著しく変化を遂げている世紀の変わり目である。娘たちは父の考え方に逆らうようにして、異教徒や革命運動に身を捧げる青年たちと次々に結婚して親元を離れてゆく。当時の多民族文化を反映して、作品にヘブライ語やアラム語、ロシア語・ウクライナ語といったスラヴ語も登場する。
小説の書かれた当時と比べ、ポグロム(ユダヤ人襲撃)やホロコースト、イスラエルへの移住によって現在のウクライナのユダヤ人は著しく減少したが、同国に根づくユダヤ文化を知ることのできる1冊である。
『おっぱいとトラクター』
マリーナ・レヴィツカ著、青木純子訳(集英社文庫)
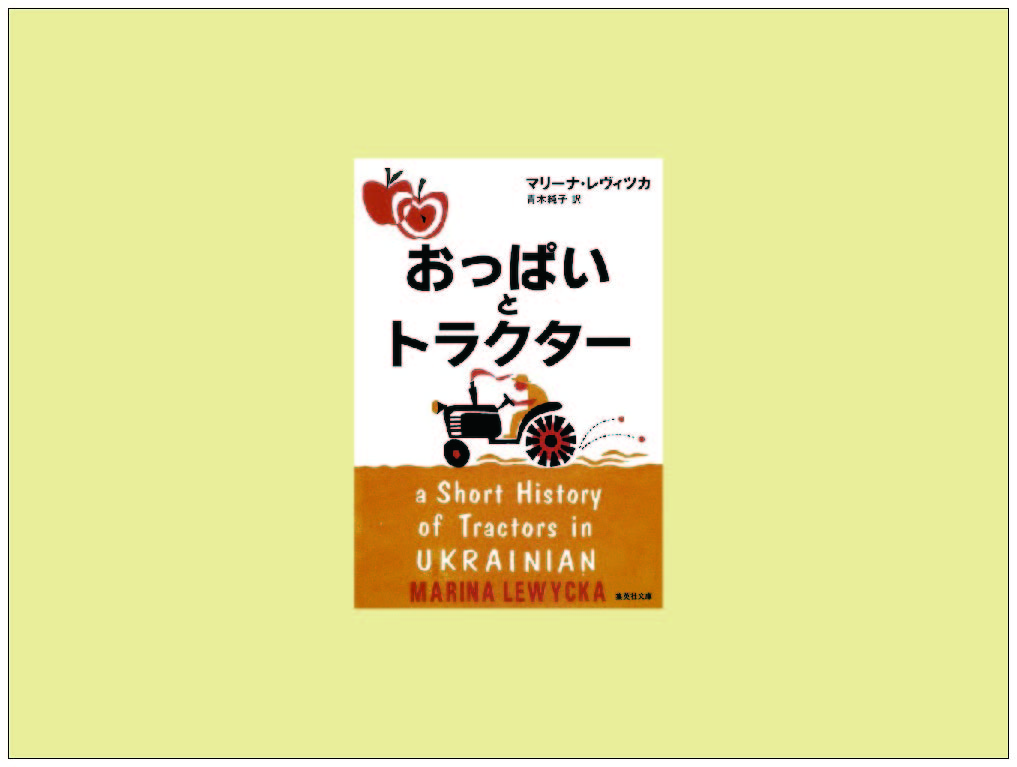 原題を『ウクライナ語版トラクター小史 A Short History of Tractors in Ukrainian』というこの小説は、イギリスで暮らすウクライナ系移民一家に突然湧き起こった家族騒動を描いている。物語は、主人公ナージャの84歳になる父親が、36歳の豊満な肉体を持つウクライナ人女性ヴァレンチナと結婚すると言い出すところから始まる。ウクライナ出身のニコライは元トラクターの技師で、ヴァレンチナは彼と結婚して財産とイギリスのパスポートを手に入れようとしている。そこでナージャは母親の遺産をめぐって骨肉の争いをしていた姉と一時休戦し、父親を守るための共闘を開始するのだった。
原題を『ウクライナ語版トラクター小史 A Short History of Tractors in Ukrainian』というこの小説は、イギリスで暮らすウクライナ系移民一家に突然湧き起こった家族騒動を描いている。物語は、主人公ナージャの84歳になる父親が、36歳の豊満な肉体を持つウクライナ人女性ヴァレンチナと結婚すると言い出すところから始まる。ウクライナ出身のニコライは元トラクターの技師で、ヴァレンチナは彼と結婚して財産とイギリスのパスポートを手に入れようとしている。そこでナージャは母親の遺産をめぐって骨肉の争いをしていた姉と一時休戦し、父親を守るための共闘を開始するのだった。著者のレヴィツカは、ドイツ・キールの難民キャンプでウクライナ出身の両親のもとに生まれたウクライナ系イギリス人で、ニコライは彼女の父をモデルにしている。ニコライの口や家族会議で飛び出す話から、ニコライたちが飢饉(後述の『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』を参照)と独ソ戦を生き延びるためどれほど必死に生きてきたか、ナージャの知らなかった真実が浮かび上がってくる。彼を救ったのは、ヨーロッパ有数の穀倉地帯で身につけたトラクター技師としての腕だった。
その受難の歴史を知ったとき、祖国からやって来た若い女性を前にしたニコライの舞い上がりぶりを、読者は単純には断罪できないのではないだろうか。ヴァレンチナが飢えとは無縁な肉体を誇っていることも重要だろう。
『火の馬』
セルゲイ・パラジャーノフ監督


写真提供:パンドラ
『火の馬』(原題『忘れられた祖先の影』)は、ウクライナの国立映画機関である国立オレクサンドル・ドヴジェンコ映画センターが2021年に選出したウクライナ映画のオール・タイム・ベストにおいて、センターにその名が冠せられているドヴジェンコ監督の代表作『大地』(1930)を抑え、堂々の1位に輝いた作品である。
監督はジョージア生まれのアルメニア人であるセルゲイ・パラジャーノフで、全編ウクライナ語で製作された。世界映画史に燦然とその名を輝かせるこの映画作家は、ウクライナとの縁が深かった。全ソ国立映画大学ではドヴジェンコらに師事し、フィルモグラフィ前半の作品のほとんどがキエフにあるドヴジェンコ記念映画スタジオで制作されている。
そしてウクライナでの映画制作の頂点とされるのが、西部のカルパティア山脈を舞台に、反目しあう一家同士の幼なじみイヴァンとマリーチカの悲恋を色彩豊かに描いた『火の馬』である。マリーチカが命を落とした後にモノクロに切り替わる瞬間は、それまでの映像が鮮やかなだけに、主人公の沈んだ心を表して痛々しい。この作品で世界的にも認知されたパラジャーノフは、次作でその先鋭化した映像を批判され、アルメニアへと拠点を移すのだった。
『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』
アグニェシュカ・ホランド監督


(C) FILM PRODUKCJA - PARKHURST - KINOROB - JONES BOY FILM - KRAKOW FESTIVAL OFFICE - STUDIO PRODUKCYJNE ORKA - KINO ŚWIAT - SILESIA FILM INSTITUTE IN KATOWICE
1933年、世界恐慌の只中にソ連だけが好景気であることに疑問を抱いたイギリス人ジャーナリストのガレス・ジョーンズは、決死の潜入取材を敢行し、秘密があるというウクライナへ向かう。そこで彼が目にするのは、ソ連指導部が粉飾して見せるうわべの景気とはあまりにかけ離れた、目を覆うばかりの光景だった。ポーランドの映画監督アグニェシュカ・ホランドが実話に基づいて撮った『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』は、当時のウクライナ国内の様子をよく知ることができる作品である。
ソ連時代のウクライナでは、旱魃や戦争、政府による強制的な穀物調達といった理由から、1920年代、30年代、40年代にそれぞれ大規模な飢饉が3度発生した。このうち、1932〜33年に起きた飢饉は、1929年に始まったソヴィエト政権下の農業集団化の過程で、富農の追放や政府による強制的な穀物調達などが原因であった。ウクライナでは「飢餓」を意味する「ホロド」と「疫病」を表す「モール」を合わせて「ホロドモール」と呼ばれ、とくに多くの被害者を生んだ。前出の『おっぱいとトラクター』の元トラクター技師ニコライは、この飢饉が農業集団化に抵抗した農民たちへのスターリンの報復だったと信じていた。ホロドモールがソ連政府によるウクライナ人を狙い撃ちしたものという説は現在は研究者によって否定されているが、人為的要因によって被害が拡大したこの悲劇がウクライナ人に与えた傷の大きさを想像させてやまない。
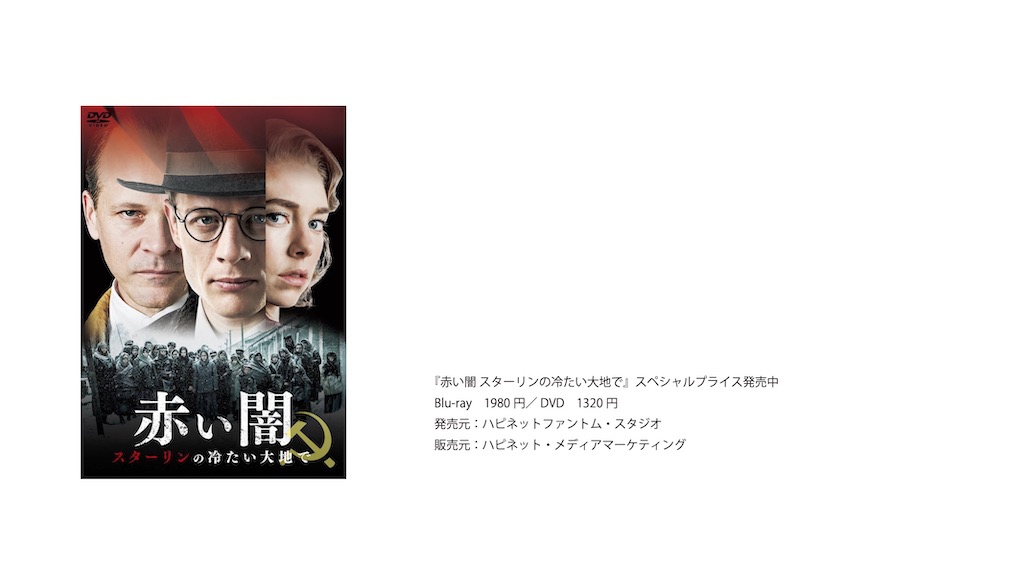
『TENET テネット』
クリストファー・ノーラン監督


Tenet © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
映画はキエフにあるオペラハウスの戦闘シーンで幕を開ける。銃撃戦の原因となっているのがプルトニウム241であることに、1986年にチェルノブイリで起きた原発事故との連想が働いていることは間違いない。2020年に公開されたこの映画の背景には、2014年に起きたロシアによるクリミア併合や東部ドンバスでの紛争を経て、ハリウッドを中心とする欧米の映画作品でウクライナが危険な場所として全世界の観客に提示されるようになってしまった側面がある。
サイモン・ウェスト監督の『コードネーム:ストラットン』(2017)では、元ロシアの諜報機関のスパイがイランで入手した生物兵器を、最初にウクライナで使用していた。フェデ・アルバレスの『蜘蛛の巣を払う女』(2018)では、主人公の天才ハッカーを追うアメリカの諜報機関に所属するセキュリティ専門家が、アフガニスタンやウクライナに駐留していたことが肩書きとして観客に紹介される。
『TENET テネット』もまた、こうした「危険なウクライナ」を提示する作品の系譜に連なっている。ヴィットリオ・デ・シーカの往年の戦後ドラマ『ひまわり』(1970)が映す、長閑な農村の風景と現在のハリウッドが描くウクライナとは、隔世の感がある。地平線の彼方まで続いていたひまわり畑のような長閑なウクライナの風景は、再びいつ映画に登場するだろうか。

梶山祐治(かじやま・ゆうじ)●筑波大学国際局グローバル・コモンズUIA。東京大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。専門はロシア文学・映画。中央アジア今昔映画祭やオンラインによるロシア・中央アジア上映会などで日本未公開作品の紹介を続けている。論文に「中央アジア映画史への招待」『中央アジア今昔映画祭パンフレット』(トレノバ、2021)など。